
家事代行サービスの歴史〜最近10年の変遷
お疲れ様です
家事代行サービスがどのように進化してきたか、気になりませんか?
忙しい現代社会で、家事をプロに任せることで生活にゆとりをもたらす家事代行サービス。
この10年間で、利用者のニーズや依頼内容が大きく変化しました。
さっそく、2010年代から2025年までの動向を見ていきましょう!
家事代行サービスの役割と市場の成長
家事代行サービスは、掃除、洗濯、料理、買い物など、日常の家事を代行するサービスです。共働き家庭や高齢者、単身者など、幅広い層が利用し、2010年代から急速に普及しました。
矢野経済研究所によると、2011年度の市場規模は約400億円でしたが、2025年には2000億円を超えるとの予測も(野村総合研究所では最大8000億円との試算も)。
この成長の背景には、社会構造や価値観の変化があります。
2010年代前半:家事代行の「特別な選択肢」時代2010年代初頭、家事代行はまだ「贅沢品」と見なされていました。
主な利用者は高所得者層で、大掃除やパーティー準備など、特別な場面での一時的な依頼が中心。
ニーズは「時間がない」「家事を楽にしたい」に集中し、特に掃除や片付けが人気でした。たとえば、年末の大掃除や引っ越し後の整理整頓を依頼するケースが多かったです。
この時期、利用へのハードルも高く、「他人に家事を任せるのは抵抗がある」「プライバシーが心配」といった声が一般的でした。
サービス提供側も、スタッフのスキルや信頼性の確保が課題で、品質のバラつきが問題に。認知度が低かったため、利用者は限定的で、業界はまだ発展途上でした。
2010年代中盤:共働き世帯の増加とニーズの多様化2015年頃から、家事代行サービスの需要が急拡大しました。
総務省のデータによると、2015年に共働き世帯が専業主婦世帯を上回り、女性の社会進出やワークライフバランスの重視が背景に。
忙しい共働き家庭や子育て世帯を中心に、日常的な家事のサポートを求める声が増えました。市場規模は2017年時点で約698億円に成長(矢野経済研究所)。
ニーズも多様化し、掃除や洗濯だけでなく、作り置き料理、買い物代行、ペットの世話などが人気に。
特に「作り置き料理」は、平日の食事準備の負担を軽減したい家庭で重宝されました。高齢者向けには、簡単な生活支援や話し相手のサービスも登場。
また、スマホアプリやウェブプラットフォームの普及により、予約が簡単になり、単発から定期契約まで柔軟な利用が増えました。
この時期、家事代行は「特別なサービス」から「日常のサポート」へと変化し始めました。
2020年代初頭:コロナ禍での新たなニーズ
2020年の新型コロナウイルス流行は、家事代行業界に大きな影響を与えました。
在宅勤務の普及で家にいる時間が増えた一方、子どもの休校やリモートワークで家事負担が増大。
特に子育て世帯では、掃除や料理の頻度が上がり、「家を清潔に保ちたい」というニーズが急増。
抗菌・除菌を重視した清掃や、換気や衛生管理に配慮したサービスが求められました。
コロナ禍では「非接触型」のサービスも注目されました。
鍵預かりボックスを使った作業や、利用者不在時のサービス提供、オンラインでの買い物代行などが増加。
さらに、食材キットの準備や、衛生的な食事提供を求める依頼も目立ちました。
この時期、利用者の意識は「便利さ」だけでなく「安全性」や「衛生面」にシフトし、業界も柔軟に対応を迫られました。
2020年代後半:日常のインフラとしての定着
2025年現在、家事代行サービスは「日常のインフラ」として完全に定着しました。
利用者は共働き家庭だけでなく、単身者、学生、高齢者、フリーランスなど多岐にわたり、特に20代〜30代の若年層の利用が顕著。
趣味や自己啓発、仕事に時間を割くため、家事をアウトソーシングする人が増えています。
「時間を買う」意識が浸透し、家事代行は生活の質を高める手段として広く受け入れられています。
ニーズはさらにカスタマイズ化。
短時間のピンポイント清掃、エコフレンドリーな洗剤の使用、ペットや子どもに配慮したサービス、ビーガンやアレルギー対応の料理など、個々のライフスタイルに合わせた依頼が主流です。
また、専門性の高いサービスも人気で、整理収納のプロによる片付けサポートや、シェフによる高品質な料理代行、引っ越し時のトータルサポートなどが増加。
利用者は単なる家事の代行を超え、「生活の質の向上」を求めています。変化を支えた社会的背景この10年間の変化を支えた要因は以下の通りです:
- 共働き世帯の増加:仕事と家事の両立ニーズが家事代行を後押し。
- 高齢化社会:高齢者の自立支援や家族の負担軽減のための利用拡大。
- 価値観の変化:家事をアウトソーシングすることへの抵抗感が減少し、「時間価値」の意識が高まる。
- テクノロジーの進化:アプリやプラットフォームで予約が容易になり、利用者とスタッフのマッチングが効率化。
今後の展望:AIとロボットの可能性今後、家事代行サービスはさらに進化するでしょう。AIやロボット技術の導入により、効率的かつ低コストなサービスが期待されます。
たとえば、自動清掃ロボットと人間のスタッフを組み合わせたハイブリッドサービスや、AIが家庭のニーズを予測して最適なプランを提案する仕組みが登場する可能性も。
また、サステナビリティを重視したサービスや、地域密着型の小規模事業者の参入も増え、選択肢がさらに広がるでしょう。
まとめ:家事代行は現代のライフパートナーこの10年で、家事代行サービスは「贅沢」から「生活の一部」へと変わりました。共働き世帯の増加、コロナ禍での衛生意識の高まり、カスタマイズニーズの台頭など、時代に合わせた進化を遂げています。
2025年現在、市場は成長を続け、利用者の多様なライフスタイルに応じたサービスが次々と生まれています。
家事代行を活用すれば、忙しい毎日でも自分の時間を確保し、趣味や家族との時間を充実させられます。
あなたも、家事代行を取り入れて、もっとゆとりある生活を始めてみませんか? 家事代行は、現代人の心強いライフパートナーです!(※参考:矢野経済研究所、野村総合研究所、総務省データ)



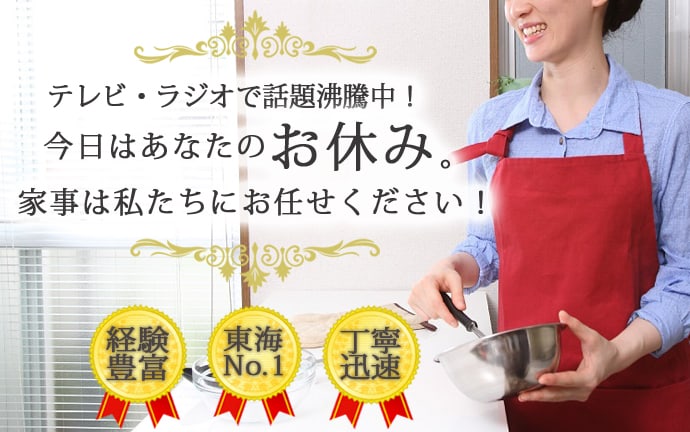


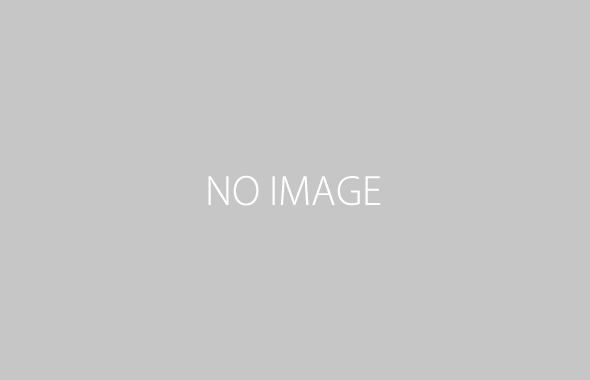
この記事へのコメントはありません。